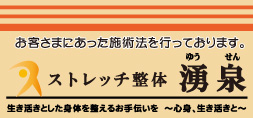*整体をするうえで健康を追求するうえで共感した考えを抜粋*
自然科学の発達によって、近代医学は解剖学を基礎とし、観察実験による実質的で合理的な体系を築き上げてきました。
この方法の特徴は、まず形がはっきりして働きの単純なものを基本として、次第に複雑なものを解明していくという手続きがとられるところにあります。
人間の最も発達している大脳の新皮質が、このような判別性感覚によって「もの」を理解するようにできているからです。
これに対して基本的な生命活動と密接に結びついている感覚は、内臓や嗅覚、痛みなどに関係した原始感覚とよばれるものです。
ものを見分けるということは、重なり合ったような二点を別々に分けて見るということですから、これを判別性感覚とよびます。
混乱した多様なものが、このようにはっきり区別されて、それぞれの有効な使い方を整然と知っていることが知性であり、その知性の論理に従うことが合理的だといえるのです。
「理」は十字のスジ目をつけて区別すること、またそのスジ目にそって玉を磨くことです。
混沌の中から、ある形を区切ってとり出し、周囲と区別して一つのまとまりにすると、それが「もの」になります。
このように周囲から切り離されて、一かたまりの形をとったとき、それが「もの」として私たちに捉えられるような姿になつのです。
これに対して「いのち」を考えてみますと、生きることが息することであるように、外を内に入れ、内を外に出すという働きです。
生命にも内と外の境はありますが、その境で切り離されたら生きていくことはできないのです。
また細胞の内部にみられるように、生きることは動くことであって、かたまった形になってしまっては駄目なのです。
内外の交流と内部の流動がありながら同じ姿を保っているところに「いのち」があります。
身体をすみからすみまで解剖してみたが、どこにも「いのち」というものは存在しなかったとある解剖学者は言ったそうです。
それは「いのち」はものとして存在しないということです。
周囲から切り取ったとき、その生命は失われて物になってしまいます。
古人は一木一草や無生の石に「いのち」を感じてきました。
それは自分とそのものが切り離された存在ではなく、一体であると感じたとき、生きて感じられたのです。
原始感覚は、そのものと自分が一つになったとき感じる感覚です。
痛みは自分の痛みであり、臭いは自分のいきづかいになったものであり、内臓感覚は自分の身体の感覚であって、そこに分離はまったくありません。
判別性感覚は自分から切り離された対象として、そこにあるもの、またかなたにあるものを見分ける感覚なのです。
「いのち」と「もの」をこの二つのあり方を混同して、生命を自分のものにしようとすれば、「いのち」は消えてなくなってしまうのです。
スジやツボは生命の基本的な働きですから、物を見るように判別性感覚で捉えようとしても摑まえることはできないのです。
触角は皮膚の判別性感覚ですから、物の姿形はわかっても、生命的な働きは見えません。
お客様と一体になって、原子感覚によりお客様の不調を共感するときに、身体を正すツボやスジが自分の身体と同様に実感されるのです。